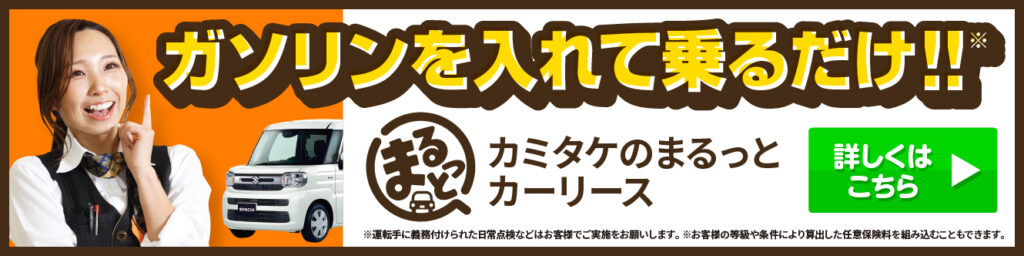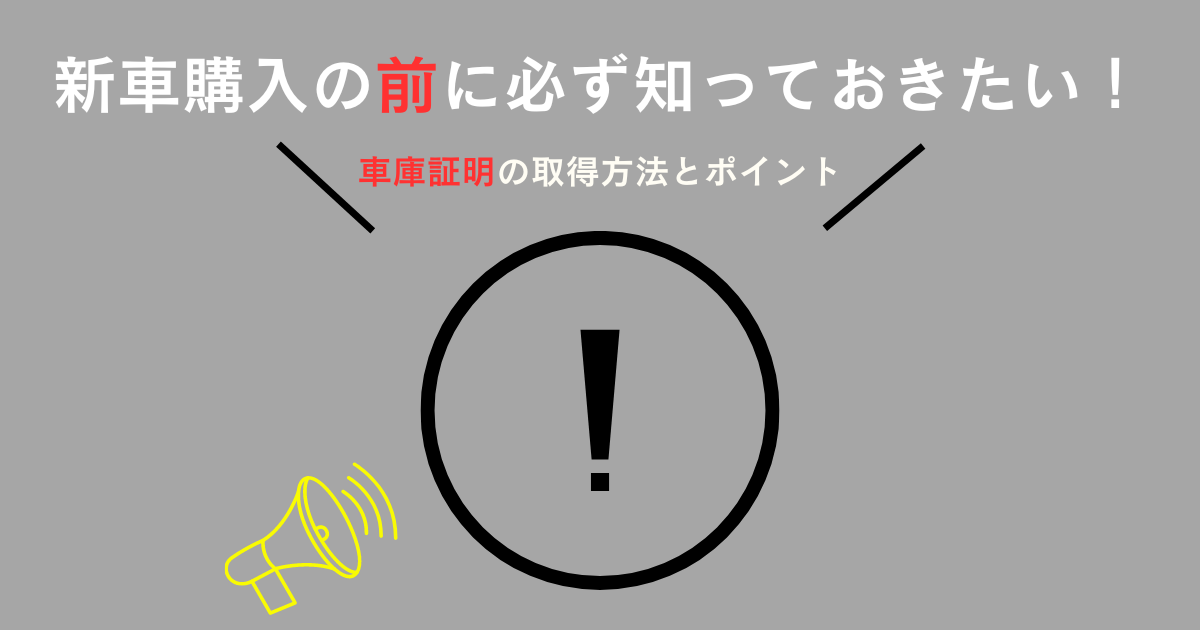車を購入する際には、「車庫証明」を取得して手続きを進める必要があります。車庫証明という言葉を知っていたとしても、どのような手続きをして取得するのか知らないという方も多いです。
そこでこの記事では、新車購入でも必要となる車庫証明の取り方や手続きの方法をご紹介します。


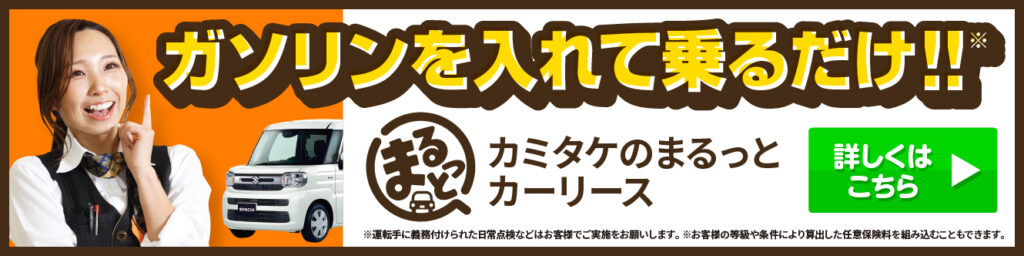
車庫証明の概要

車庫証明書というのは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。これは車庫法とその施行規則で定められていて、車の保管場所がしっかり確保されていることを証明する書類です。
新車でも中古車でも、新しく車を購入したり、所有者が変わったり、住所や事業所を移転したりした場合には、その地域を管轄している警察署で「保管場所証明申請手続」をしなければなりません。そして、この手続きを終えると、車庫証明書が発行されます。
この制度があるのは、公道での違法駐車を防ぐためです。しかし、地域によっては手続きが不要な「適用除外地域」というのもあり、どこがそうなのかは都道府県警察のウェブサイトで確認できます。
また、普通自動車で所有者や住所はそのままで、保管場所だけを変更した場合には、車庫証明書を取り直す必要はありません。その場合は、警察署で「保管場所届出手続」を行えば良いです。

車庫の条件
車を置くスペース(車庫)として認められるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。特に賃貸マンションの駐車場ではなく、自分が所有するスペースを使う場合には注意が必要です。
- 車の使用拠点から2km以内(直線距離)にあること。
- 道路から問題なく出入りできて、車全体が収まること。
- 車の所有者が、その場所を保管場所として使う権利を持っていること。
ここでいう「本拠」というのは、車の所有者が実際に住んでいる場所のことです。一般的には車検証に書いてある住所となります。もし、この条件を満たしていないのに虚偽の申請をした場合、罰則の対象になるので注意しましょう。
軽自動車は届出となる
車庫証明は、普通自動車と軽自動車で名前が異なります。普通自動車は国に登録するので「車庫証明」と呼びますが、軽自動車は軽自動車検査協会に「届出」するので「保管場所届出」といいます。しかし、名前が異なるだけで、手続きの内容や役割はほとんど同じです。
適用除外地域がある
車庫証明には、手続きが不要な地域(適用除外地域)もあります。大都市では必要ですが、本拠が適用除外地域にある場合には手続きが不要です。適用除外地域は都道府県ごとに決まっており、軽自動車と普通自動車で対象地域が異なることもあります。
軽自動車の保管場所届出は「使用の本拠地の県庁所在地の人口が10万人以上」の場合に必要になることが多いです。普通自動車よりも適用除外地域が多くなる傾向がありますが、これはあくまで目安なので、実際に車を購入する際には確認することをおすすめします。
車庫証明が必要な理由

自動車を所有する際には、駐車場所を確保しておく必要があります。「車庫法」という法律があり、自動車の保有者は必ず自動車の保管場所を確保するように、定められているからです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
車庫証明が不要で、自動車の保管場所が決まっていない車が増えてしまうと、路上駐車が多くなり交通に支障をきたします。
また家の前や他の場所に許可なく駐車してしまう人が増えてしまう可能性もあるでしょう。そのため、自動車を購入したり、登録したりするときにきちんと車を駐車するスペースを確保していることを証明する車庫証明が必要です。
車庫証明の取得手続き

必要書類一覧
車庫証明に必要書類は、以下の通りです。
- 保管場所標章交付申請書
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 使用者の本拠地を確認できる書類
保管場所使用承諾証明書は月極駐車場の場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)は自己所有の土地で車庫証明を取得するときに使用します。
取得手続きの流れ
申請書類をもらう
まず、車庫証明の申請書類は車を保管する場所を担当する警察署で手に入れます。新車や中古車を購入する際には、ディーラーが申請書類を準備してくれることもあります。警視庁などのホームページからダウンロードできる場合もありますが、複写式の書類を使いたい場合は警察署に行って受け取る必要があります。
必要書類の準備
申請書類を手に入れたら、必要事項を記入して書類を作成します。車の保管場所がご自身の土地か、借りている場所かで準備する書類が異なりますので注意してください。申請時に記入漏れがあると受理されないことがありますので、申請書類にある記入例を参考にして確実に記入するようにしてください。
車庫証明を警察署に申請
書類が完成しましたら、車の保管場所を担当する警察署に提出・申請します。書類の事前チェックは必須ですが、不備があった場合その場で修正できるように認印を持参すると良いでしょう。申請の際には手数料がかかります。申請書が受理されると「納入通知書兼領収書」がもらえます。これは後日、車庫証明を受け取るための引換券になりますので、大事に保管してください。
車庫証明を受け取る
証明書や標章の交付は、通常3日から7日程度かかります。申請した警察署で証明書類を受け取る際には、「納入通知書兼領収書」を持参してください。また、標章交付手数料として約500円が必要です。郵送で受け取れる場合もありますので、警察署の窓口で確認してみてください。
交付される書類
車庫証明の手続きが完了すると、警察署から以下の3つの書類が交付されます。
- 自動車保管場所証明書
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
まずは、警察署長の公印と日付が記入されているか確認しましょう。証明書は、運輸支局で自動車登録を行う際に必要ですので、ディーラーに登録を依頼している場合はディーラーに渡してください。通知書は車検証などと一緒に大切に保管してください。
車庫証明の書き方

- 保管場所標章交付申請書
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 使用者の本拠地を確認できる書類
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、「自動車保管場所証明申請書」と似た内容を記入するものです。警察署でこの書類を入手した場合、正本と副本がそれぞれ2枚ずつ、合計4枚の複写式になっています。一方、ネットからダウンロードして印刷した場合は、1枚ずつ記入して用意する必要があります。
自動車保管場所証明申請書
車庫証明を取得するために必要な自動車保管場所証明申請書の書き方について説明いたします。手続きが完了すると、車庫証明書が発行されます。
まず、「車名」、「型式」、「車台番号」、「自動車の大きさ」は車検証に記載されている通りに正確にご記入ください。「自動車の使用の本拠の位置」には、車の所有者が実際に住んでいる住所を記入します。
「自動車の保管場所の位置」には、車を停める駐車場の住所を記入してください。「保管場所標章番号」は、以前と同じ住所や駐車場で、乗り換えや再取得の場合に記入します。新しく申請する場合は空欄で構いません。
次に、「申請者」欄には、車を使用する方の住所や名前を記入します。そして「所有区分」と「連絡先」も忘れずに記入してください。もし車を買い替える場合は、現在使用している車の登録番号と車台番号も記入しましょう。
このようにして申請書を正確に記入することで、車庫証明をスムーズに取得することができます。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図は、車をどこに保管するかを図で示すものです。まず、所在図の欄には、自宅と保管場所の位置がわかる地図を載せます。初めての人でも迷わないように、目印となる建物も一緒に記載します。警察署によっては、住宅地図のコピーでも対応してもらえることがあります。
次に、自宅と保管場所との直線距離を測定して書き込みます。Google Mapなどの地図アプリを使えば、二点を指定するだけで簡単に測定できます。
配置図の欄には、保管場所の詳細を記載します。たとえば、自宅の敷地内に保管する場合、その位置関係や保管場所の大きさ、側道の幅などを記載します。空地や駐車場の場合は、全体の広さや駐車スペースの番号・広さ、出入口や側道の幅、隣接する建物などを記載します。立体駐車場の場合は、地上からの高さも必要です。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾書は、自分の土地ではなく、賃貸や月極駐車場に車を置くときに必要な書類です。他人の土地を借りて駐車している場合、その土地の所有者に住所と名前を書いていただき、印鑑を押してもらいます。
もし、その土地が共有されている場合は、共有者全員の住所と名前、それに印鑑が必要になります。しかし、共有者が多くて書ききれない場合は、別の紙に書いて、保管場所使用承諾書には「別紙記載」とだけ書けばよいでしょう。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の所有者がご自身である場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入はとても簡単です。車庫証明を申請する警察署の名前と申請日、そしてご自身の住所と名前を記入し、最後に印鑑を押すだけです。
もしご自身の土地に車を置いていて、その土地の所有者がご自身なら、この書類を作成するのはとても簡単です。警察署の名前と申請日を書いて、次にご自身の住所と名前を書き、印鑑を押すだけで問題ありません。上記の手続きを進めるだけで、車庫証明の申請がスムーズに進みます。
使用者の本拠地を確認できる書類
車庫証明を申請するときには、その車を実際に使う人が自分の住所に住んでいるかどうかを証明する書類が必要になります。たとえば、電気代やガス代の領収書、または自分の住所に届いた消印付きの郵便物が使えます。
車庫証明の取得に必要な費用
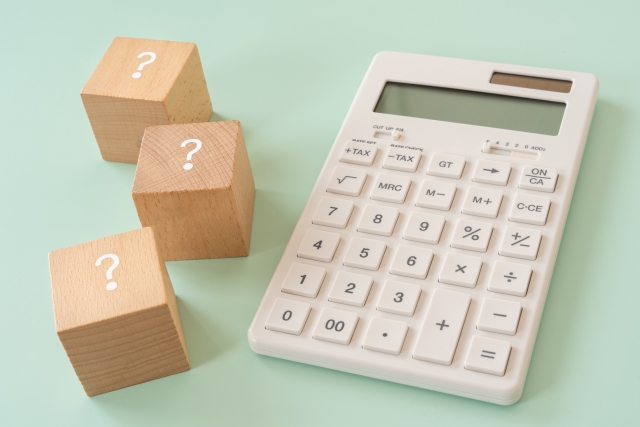
車を購入する際に、ディーラーや中古車販売店が車庫証明を代行で取得してくれることが多いです。ただし、その手続きにかかる費用は車の本体価格とは別になることがほとんどです。見積もりを取る際に、手続き手数料として記載されているはずなので確認してみましょう。
たとえば、ディーラーや中古車販売店に車庫証明の取得をお願いすると、代行手数料はおおよそ数千円から2万円になります。
一方、車の所有者自身で車庫証明を取得する場合は、警察署での手続きになります。その際の費用は、保管場所証明申請手数料が2,200円、標章交付申請手数料が500円、合計で約2,700円です。

取得時の注意点

所有者の現住所と申請の住民票住所地が違う場合は注意する
車の所有者が現在住んでいる場所と住民票の住所が違う場合、例えば長期出張や赴任などの理由で異なる場合は、その理由を説明する必要があります。基本的には、使用者の居住地と申請者の住所は住民票と同じであることが求められ、免許証や住民票で確認されます。
そのため、単身赴任などで県をまたぐ場合などは、実際にそこに住んでいることを証明するために、公共料金の請求書や家賃の領収証などを用意しておくとよいでしょう。
申請する前に、実際に住んでいる場所と住民票の住所が異なる場合にどんな書類が必要になるか、警察署に確認しておくことをおすすめします。
月極駐車場なら断りを入れる
貸主に無断で賃貸契約書を車庫証明に使用するとトラブルになりやすいです。なぜなら、車庫証明をすると、同じ場所で再度車庫証明を使えるのは6か月後になるからです。
万が一、それより前に駐車場の契約を解除した場合、新たな利用者は車庫証明の申請ができません。契約している駐車場の貸主や次の利用者に迷惑をかけてしまうため、必ず貸主に断りを入れるのがマナーです。
駐車スペースの広さをチェックする
車を購入する前に、駐車スペースが十分に広いかを確認することが大切です。書類上では車のサイズに合っている駐車スペースでも、実際には人の乗り降りがしにくいくらいギリギリですと、申請が下りないことがあります。駐車スペースには、車を停めても余裕がある広さが必要です。
特に3ナンバーサイズの車が増えてきて、駐車スペースに駐車すると隣の駐車スペースとの距離が短いことがあります。事前に駐車場を確認しておきましょう。
事前に契約を済ませておく
駐車場を借りる場合、車庫証明の申請前に賃貸契約を結んでおく必要があります。ただし、契約のタイミングに注意が必要です。例えば、下見をしないと、希望するスペースがすでに埋まっていることがあります。また、車がないうちに賃貸料の支払いが始まることもありますので、しっかりとタイミングを計って契約しましょう。
車庫飛ばしにならないように注意する
車庫証明は、実際に車を保管する場所で申請しなければなりません。例えば、近くの月極駐車場や実家の駐車スペースで申請して、実際には自宅の近くに車を停めるようなことは「車庫飛ばし」と呼ばれ、違法です。これに違反すると、最悪の場合「3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金」といった重い罰則が科せられることがありますので、注意が必要です。
よくある質問
- 車庫証明は必要?
-
車を買うときには「車庫証明」が必要です。これは「自動車保管場所証明書」とも言われ、簡単に言うと「この車を置く場所があります」という証明書です。車を買うときに、この証明書を警察に提出しなければなりません。軽自動車の場合は地域に左右されます。
- 車庫証明はいつまでにどうやって用意したらよい?
-
車庫証明の申請は、車を買う契約を結んだ後に行います。証明書が発行されるまでに最大2週間ほどかかることもあるため、契約が終わったらすぐに手続きを始めた方が良いです。申請は車を置く場所の近くの警察署で行います。手数料として収入印紙を購入し、書類と一緒に提出します。