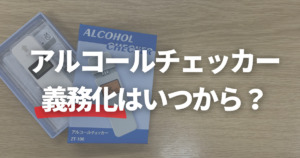お酒を飲んだら運転しないのはもちろんですが、一体どのくらいの時間が経ったらアルコールがぬけるのか気になるものです。
一晩寝ればアルコールはぬけると判断している方は多いですが、深夜まで飲んでいたなら、朝起きたときに本当にアルコールがぬけているのか心配になります。
飲んでいるお酒もアルコール度数が異なっているため、アルコールがぬけるまでの時間もさまざまです。そこでこの記事では、飲酒後にアルコールがぬけるまでの時間の目安をご紹介します。
※飲酒後にアルコールがぬけるまでの時間は、目安となっています。アルコールが消失する時間が経っていたとしても、体調や体質によっても状況が異なるので注意しましょう。
飲酒後にアルコールがぬけるまでは何分?

そもそもアルコールを摂取すると、胃や小腸などの体内の消化管によって吸収されていきます。その後、肝臓の酵素の働きにより、アルコールが分解されていきます。
分解された成分は、筋肉などの肝臓外の組織でさらに分解されていくという仕組みです。つまり体内に取り入れたアルコールは、複数の過程を経て分解されていきます。
分解されなかったアルコール成分は、血液に溶け込んで脳に到達します。飲酒後に酔ってしまうのは、このような過程を経ているからです。
そして、徐々にアルコールが分解されて、「ぬけた状態」となっていきます。アルコールを飲んだ後に、ぬけるまでに時間が必要なのは、このような働きになっているからです。
一般的に体重が60kgほどの人の場合は、350mlの缶を飲むと、アルコールが分解されるまで2時間半ほど要するとされています。
アルコールが分解されてしまえば、運転も可能な状態になりますが、アルコールがぬけたとしても運転できる状態なのかは個人差があります。
アルコールが分解できる時間の計算方法

アルコールが分解できる時間は、体重や摂取したお酒の量で判断できます。個人差は有りますが、アルコールがぬけるまでの目安を計算できるでしょう。
アルコールが分解できるまでの時間の計算式
「摂取した純アルコール量(g)÷(体重kg×0.1)=アルコールが分解できる時間」
純アルコール量とは、お酒のどのくらいのアルコールが含まれているかを示す数字です。
たとえば、純アルコール量20gのアルコール度数5°のビールを中びん1本飲んだとします。体重60kgの人が中びん1本飲むと、アルコールが分解できる時間が約3.3時間となります。
もし中びん2本飲むと、アルコールを分解するまでに6.6時間も必要です。少し休憩したからといって、すぐにぬける時間ではないため、十分に注意しましょう。
アルコールが分解できるまでの時間は、一般的な飲酒量や体調の人の目安です。年齢やアルコールの分解能力によって個人差が発生するため、計算式で割り出した時間でも注意します。
アルコールを分解できる時間の個人差
お酒に対する強さは、個人差があります。一般的には女性よりも男性の方がアルコールの分解能力が高い傾向があります。また体重も軽い人よりも、重い人の方が血中アルコール濃度が低くなるので、酔いにくい傾向がありますが、あくまでも目安のなので注意が必要です。
もちろんアルコールに強いからといって、臓器への影響がなくなる訳ではないので、バランスを取りましょう。
飲酒運転の罰則は?

アルコールを摂取した後に運転すると、正しい判断ができなくなるため、非常に危険です。重大な事故につながる可能性もあるため、道路交通法で主気帯び運転として罰則が設けられています。
行政処分
酒酔い運転
基礎点数 35点 免許取り消し 欠格期間3年
酒気帯び運転呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(※2)
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(※2,3)
※警視庁
罰則
車両等を運転した者
酒酔い運転をした場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供した者又は同乗した者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※警視庁
※警視庁
このように、アルコールを飲んだ後に運転すると、運転した本人はもちろんですが、車両を提供したり、同乗するだけでも罰則があります。
飲酒運転による死亡事故は、減少傾向にあるものの、それでも数多くの事故が起きています。
また、飲酒運転の死亡事故率は飲酒無しの約7.1倍という数値も出ているほど、危険性が高いです。
厳しい罰則があるだけでなく、自分や他の人の人生にまで影響を与える可能性があるため、飲んだら運転せずに代行運転サービスなどを利用しましょう。
お酒の種類別|アルコール量の目安

お酒の種類によって、アルコール量は異なっています。アルコール度数が異なるため、種類によって度数が異なることを覚えておきましょう。
厚生労働省の「健康日本21」の中で、1日に摂取するお酒の量として、純アルコール量20gが基準とされています。
純アルコール量20gのお酒の種類別の量は、以下の通りです。
純アルコール20gのお酒の量の表
ビール (5度)中びん1本 500ml
日本酒 (15度)1合 180ml
焼酎 (25度) 0.6合 約110ml
ウイスキー(43度) ダブル1杯 60ml
ワイン (14度) 1/4本 約180ml
缶チューハイ (5度) ロング缶 1缶 500ml
これらを基準にして、どれほどお酒を飲むのか調整するのをおすすめします。
アルコールを早くぬく方法はあるの?
結論からすると、アルコールを早くぬく方法はありません。水分を補給すればアルコールが薄くなると感じますが、実は血中のアルコール濃度は摂取した水分では変化しないので注意が必要です。
前述したように、アルコールは肝臓で分解されていくため、水分では変化しないのです。アルコールを早くぬくためには、そもそも飲む量を抑えるのが一番となります。
しかし缶ビール1本を飲んだとしても、アルコールが完全に分解されるまで時間が必要です。さらに、アルコールが分解されるとされる時間が経過しても、体調や体質によっては分解できていないこともあるため、早くぬく方法はないと覚えておきましょう。
飲酒運転は絶対しない!させない!許さない!見逃さない!
アルコールを摂取すると、分解されるまでに時間が必要なことが分かります。さらに、基準となる純アルコール量20gを超えて飲酒すると、完全に分解されるまで時間がかかるため、飲んだら乗るなを徹底しなければいけません。
アルコールが分解されるまでの時間の目安はありますが、体調や体質によっては分解できていないこともあるため、運転代行サービスなどの利用を検討しましょう。個人差があるアルコールの分解時間ですが、飲み過ぎないことが一番の対策なので、上手に飲酒と付き合うようにすることをおすすめします。