都心部に限らず地方部でも「ETC専用化」が急速に普及しています。
料金所のタッチレス化とキャッシュレス化の実現に向けて、首都高やNEXCOの料金所では2025年までに数十件から数百件単位でETC専用化が予定されています。
今後のETC専用化に向けて私達が取り組むべきことは何なのでしょうか。
「ETC専用化による利用者のメリットとデメリットはどこにあるのか」や「最新のETC専用化の推進情報」を解説します。
ETC専用化が進んでいる3つの理由

ETC専用化が進んでいる理由は3つあります。
- 渋滞時に混雑軽減
- 感染症リスクの軽減
- キャッシュレス化・タッチレス化の推進
それぞれの理由を詳しく解説します。
渋滞時の混雑軽減

ETC専用化を進める1つめの理由は「渋滞時の混雑軽減」です。
ETC専用化に対する取り組みには「戦略的な料金体制の導入による渋滞軽減」が実施されています。
具体的には混雑時の高速利用料金を高めに設定し、閑散時の利用料金を安くするシステム導入により「交通量の平準化」を目指す取り組みです。
渋滞軽減の料金システムを採用することで、高速道路の利便性の向上を期待できます。
感染症リスクの軽減
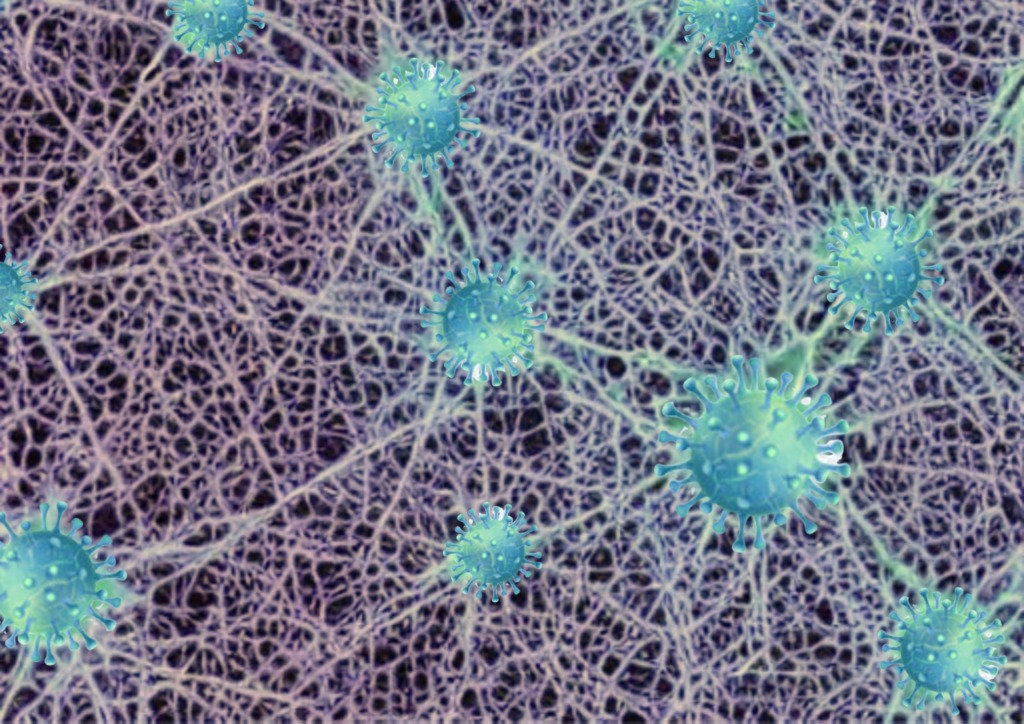
ETC専用化により料金支払いのタッチレス化がさらに普及します。
タッチレス化の導入が本格化すれば、窓口対応による接触頻度が少なくなるため、結果的に感染症リスクの軽減に繋がります。
ETC専用化は利用者や専用窓口の対応スタッフのためにも、感染リスクを最小限に抑えられる対策方法の1つです。
キャッスレス化・タッチレス化の推進

ETC専用化により「キャッシュレス化・タッチレス化の推進」が期待されています。
キャッシュレス化やタッチレス化は、料金所の窓口対応による人件費削減や高速道路の利便性向上にも繋がります。
ETC専用化の普及には、ETCカードの普及が必要不可欠なため、ETC カードの普及やETC車載器の取り付けも関係してきます。
ETC専用化のメリット

ETC専用化のメリットは3つあります。
- ETCカードの普及率アップ
- 管理コストの削減
- 様々な支援や楓宮処置が実施される
それぞれのメリットを詳しく解説します。
ETCカードの普及促進

現在、ETCカードの利用率は全体で8割を超えている状況です。
しかし、残りの約20%は現在でも「非ETCユーザー」として高速道路やETC専用道路を利用しています。
ETC専用化が進めば、ETC利用率も100%に近い数値を記録できると期待されています。
※国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/pdf/7.pdf)
管理コストの削減

ETC専用化が今後も普及するとキャッシュレス化が進みます。
結果的には、料金所での対応スタッフに対する人件費が削減できるため、管理コストの削減に繋がります。
首都高を中心にETC専用化が進んでいますが、導入コスト以上に「人件費の削減の効果」が期待できると言われています。
様々な支援や優遇処置が実施される

今後のETC専用化に伴い、政府は様々な「車載器購入助成金」や「ETCパーソナルカードのデポジットの下限の引き上げ」などの優遇施策を実施する予定です。
優遇施策の効果は限定的と言われていますが、ETC専用化に対して「ETCカードの普及」や「渋滞時間の利用軽減」に繋がれば、利用者の利便性はさらにアップするでしょう。
※国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378536.pdf)
ETC専用化のデメリット

ETC専用化のデメリットは3つあります。
- 非ETCユーザーが高速道路を利用できなくなる
- 現金支払いができない
- 万が一のETC機材トラブルのために係員が必要
ETC専用化のメリット以外にデメリットも理解しておきましょう。
非ETCユーザーが高速道路を利用できなくなる

ETC専用化が今後も普及すると、現金支払いに対応できる料金所が減少します。
現金支払い対応の料金所が徐々に減少すると、結果的に非ETC所有ユーザーは高速道路の利用不可になる訳です。
ETC専用化はキャッシュレス化や料金所の人件費削減などに効果的な方針ですが、ETCを使用しない方には不便な取り組みになります。
現金で支払いができない

ETC専用化が進むと、ETC道路の利用を「現金で支払いができない」ことに繋がります。
高速道路を利用する方の中にも「ETCカードを利用しない方」も中にはいます。
ETC専用道路を利用する場合にはETCカードの作成が必ず必要になる時代が着々と近づいています。
万が一のETC機材トラブルのために係員が必要

どんなにETC専用化が普及しても、料金所の料金スタッフをゼロにはできません。
理由としては、万が一、ETC機材トラブルが発生した場合に対応できる係員が必要になるからです。
キャッシュレス化やタッチ決済型に対応した機器は高度な制御装置やシステムを多数搭載しています。
少しでもシステム操作に異常が発生すれば、結果的にETC機材のトラブルに発展する可能性が高いです。
ETC専用化に対する今後の推進

ETC専用化に対する今後の推進を「都心部」と「地方部」に分けて解説します。
【都市部】ETC専用化に対する推進情報
ETC専用化に対する都心部の推進情報としては以下を参考にしてください。
| 【都心部】 | 【推進情報】 |
| 都市部(首都圏) | ・首都高速:2025年までに160箇所程度のETC専用化に対応する設備導入予定 ・NEXCO東日本:2025年までに90箇所でETC専用化に対応する設備導入予定 ・NEXCO中日本:2025年までに20箇所でETC専用化に対応する設備導入予定 |
| 都心部(中京圏) | 2025年までに60箇所のETC専用化に対応する設備導入予定 |
| 都心部(近畿圏) | 阪神高速:2025年までに110箇所のETC専用化に対応する設備導入予定 NEXCO西日本:2025年までに70箇所のETC専用化に対応する設備導入予定 |
※国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378536.pdf)
【地方部】ETC専用化に対する推進情報
次に地方部のETC専用化に対する推進情報を解説します。
詳しくは以下の表を参考にしてください。
| 【地方部】 | 【推進情報】 |
| NEXCO3社・本四高速 | 運用状況や各地域の特性等を考慮して順次拡大予定 |
※国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378536.pdf)
【社外品】「ETC専用化対策」におすすめするETC車載器
急速に普及するETC専用化に対策するためにおすすめするETC車載器を2つ紹介します。
- 【パナソニック】CY-ET2010D
- 【ケンウッド】ETC-N3000 ETC2.0車載器
それぞれのETC車載器を詳しく解説します。
【パナソニック】CY-ET2010D

画像引用元:CY-ET2010D Panasonic
1つ目におすすめするETC車載器は「【パナソニック】CY-ET2010D」です。
【パナソニック】CY-ET2010Dは、新セキュリティに対応したETC2.0車載器であり、ナビ連動タイプとしても活用できます。
機能面はアンテナのLEDでETCカードの挿入状態をお知らせくれる機能やナビ画面で利用料金や渋滞情報を把握できる機能が搭載されています。
取り付け位置も別売オプションの「アンテナ取付ブラケット」を購入すれば、運転席の足元やコンソールボックスの中など、様々な位置に取り付けできます。
新セキュリティに対応しており、取付位置の自由度を重視したい方におすすめするETC車載器です。
【ケンウッド】ETC-N3000 ETC2.0車載器

画像引用元:ETC-N3000 | KENWOOD
2つ目におすすめするETC車載器は、【ケンウッド】ETC-N3000 ETC2.0車載器です。
【ケンウッド】ETC-N3000 ETC2.0車載器は、カーナビと連動機能ができるETC2.0に対応した車載器です。
渋滞回避や安全運転支援情報など、新セキュリティに対応したサービスを利用できます。
他にも、ETCカードの挿し忘れや有効期限の確認もできるため、乗車中から降車まで運転手をサポートしてくれます。
ETC車載器以外の利便性を重視したい方におすすめする商品です。
ETC専用化についてよくある質問
ETC専用化についてよくある質問をまとめました。
- ETC専用化が進んでいる理由とは?
- ETC専用化のメリットとデメリットは?
- ETC専用化に対する都会部と地方部の今後の推進情報は?
それぞれ詳しく解説します。
- ETC専用化が進んでいる理由とは?
-
ETC専用化が進んでいる理由は「渋滞時の利用軽減」と「感染リスクの軽減」です。
料金所のタッチレス化とキャッシュレス化の実現に向けて、首都高やNEXCOの料金所では2025年までに数十件から数百件単位でETC専用化が予定されています。
- ETC専用化のメリットとデメリットは?
-
ETC専用化のメリットは「ETCカードの普及」と「管理コストの削減」です。
デメリットは「非ETCユーザーが高速道路を利用できなくなる」ことや「現金支払いができない」などが挙げられます。
- ETC専用化に対する都会部と地方部の今後の推進情報は?
-
都心部の首都高速では、2025年までに160箇所、NEXCO東日本は90箇所、NEXCO中日本は20箇所の導入を予定しています。
一方、地方部は2025年までに運用状況を考慮して徐々に推進していく予定です。
ETC車載器の取り付けならカミタケモータースへお任せ!
ETC車載器の取り付けなら弊社カミタケモータースへお任せください。
カミタケモータースでは、ETC専用化に伴い、ETC車載器の取り付けにも力を入れています。
社外部品のETC車載器の取り付けでも問題ありません。
経験と知識が豊富な整備スタッフが、社外品のETC車載器の取り付けも気軽に対応できます。
ETC車載器の取り付け以外にも「ETCセットアップ手続き」にも対応可能です。
カミタケモータースへETC車載器と車を持ってきて頂ければ、すぐに対応させていただきます。
まずは電話でのご相談でも可能です。ぜひこちらからお問い合わせください。



