軽自動車と普通車は、軽自動車が維持費が安く、車体も小さいというイメージがありますが、実際にどのような違いがあるでしょうか?サイズはもちろんのこと、維持費も異なってきます。
短期的であれば大きな違いはないかもしれませんが、長期的に維持するとなると大きな違いが生まれることもあります。この記事では、軽自動車と普通車の違いを詳しく解説します。


軽自動車と普通車の基本的な違い

軽自動車と普通車には、法律による定義の違いや規格の大きさの違いがあります。
軽自動車と普通車の定義
普通車
実は「普通車」という言葉は法律によって定義が異なります。道路交通法では、普通車は「車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満、車両定員が10人以下の車」と定められています。
しかし、一般的に「普通車」と言う場合は、道路運送車両法に基づいた区分を指していることが多いです。この法律では、「軽自動車、小型自動車、大型特殊車両、小型特殊車両以外の自動車」が普通車とされています。簡単に言えば、軽自動車よりも大きい乗用車が普通車と考えられます。
さらにナンバープレートの番号で区別することができ、「3ナンバー」が普通乗用車、「5ナンバー」や「7ナンバー」が小型乗用車と呼ばれますが、どちらも普通車に含まれます。
軽自動車
一方、軽自動車は、日本独自の規格で作られている車です。道路運送車両法では、軽自動車は「全長が3.4m以下、全幅が1.48m以下、全高が2m以下」の車体サイズで、エンジンの総排気量は660cc以下と定められています。
また、乗車定員は4人以下、貨物積載量は350kg以下という基準があります。普通車に比べると車体が小さく、エンジンの排気量も小さいのが特徴です。そのため、狭い道路での運転がしやすく、税金も軽減されるといったメリットがあります。
車両サイズの違い
普通車の車体の大きさについても規定があり、長さが3.4mを超えて4.7m以下、幅が1.48mを超えて1.7m以下、高さは2m以下となっています。また、ナンバープレートの分類番号が500番台であるため、「5ナンバーサイズ」と呼ばれることが多いです。
一方、小型乗用車を超えるサイズの「普通乗用自動車」は、車体の長さが4.7m以上、幅が1.7m以上、高さが2mを超える車です。ナンバープレートの分類番号は300番台で、「3ナンバーサイズ」と呼ばれます。
このように、5ナンバーと3ナンバーはエンジン排気量や車体のサイズで区別されていますので、どちらに該当するかはナンバープレートを見ると簡単に確認できます。
軽自動車は、定員が4人以下で、車のサイズにも規定があります。全長が3.4m以下、全幅が1.48m以下、全高が2.0m以下と定められています。また、貨物積載量は350kgまでです。
さらに、車種によっても異なりますが軽自動車の最小回転半径は約4.4mですので、日本の狭い道路でも運転しやすい点が大きな魅力です。
エンジン排気量の違い
普通車の中には「小型乗用自動車」というカテゴリーがあり、これはエンジンの排気量が660ccを超えて2000cc以下の車を指します。2000ccを超える排気量の車は、普通乗用自動車です。
軽自動車は、エンジンの総排気量は660cc以下というコンパクトな規格になっています。
軽自動車と普通車の維持費の違い

税金の違い
軽自動車と普通車の維持費には、多くの違いがあります。特に、税金や高速料金が大きなポイントとなります。
まず、普通車の場合、自動車税は排気量に応じて異なり、2万5000円から11万円程度の幅があります。これに加えて、自賠責保険は約1万1500円かかります。また、自動車重量税は車の重量や経過年数によって異なりますが、最低でも8200円程度必要です。
一方で、軽自動車は維持費がかなり抑えられます。自動車税は一律で1万800円、自賠責保険は1万1440円、自動車重量税は3300円となっており、普通車に比べて負担が軽くなります。
自動車保険料の違い
車を所有する際には、必ず加入しなければならないのが自賠責保険です。それに加えて、任意で加入できる自動車保険もあります。この保険料は、年齢や職業などの条件によって変わるため、具体的にいくらとはいいにくいのが特徴です。
しかし、軽自動車の場合、事故を起こしても車の重量が軽いため、相手に与える損害が少ないとされています。そのため、普通車に比べて保険料がやや安くなる傾向があります。おおよその目安として、軽自動車の任意保険料は年間約35,000円、普通車の場合は約70,000円といわれています。(年齢や等級、加入条件などによって異なる場合があります。)
このように、軽自動車は全体的にコストを抑えたい方にとって、保険料を含めて魅力的な選択肢となります。
車検費用の違い
車検は、新車を購入してから最初の3年目に、その後は2年ごとに受けることが義務付けられています。その際にかかる費用には、車検の基本料金に加えて、自動車重量税や自賠責保険料といった法定費用が含まれます。
軽自動車の車検費用が安いと言われる理由は、軽自動車の基本料金や法定費用が普通車に比べて低く設定されているためです。基本料金は業者によって異なりますが、軽自動車の車検費用はおおよそ66,000円、1.5トンまでの普通車では約88,000円が目安となります。
これを2年に1度として、1年分の費用に換算すると、軽自動車は約33,000円、普通車は約44,000円となります。これにより、軽自動車の方が維持費が安いことがわかります。
弊社カミタケモータースでは車検も実施していますが、車種別の費用は以下の通りです。
| 車種 | 車検料 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計金額 | 最大割引合計金額 |
| 軽自動車 | 14,850 | 17,540 | 6,600 | 1,600 | 40,590 | 36,190 |
| 小型乗用車 | 14,850 | 17,650 | 16,400 | 1,600 | 50,500 | 46,100 |
| 中型乗用車 | 14,850 | 17,650 | 24,600 | 1,600 | 58,700 | 54,300 |
| 大型乗用車 (車両重量2,000kg以下) | 14,850 | 17,650 | 32,800 | 1,600 | 66,900 | 62,500 |
| 大型乗用車 (車両重量2,500kg以下) | 14,850 | 17,650 | 41,000 | 1,600 | 75,100 | 70,700 |
車両の大きさによって、最大約3万円ほどの差額が発生しています。また全体としては低価格で車検を受けていただける地震がございますので、維持費を抑えていただけます。車検については、こちらからお問い合わせください。
軽自動車と普通車の走行性能の違い

走行性能については、車ごとの設計やコンセプトが異なるため、軽自動車と普通車を単純に比較することは難しいです。しかし、エンジン排気量や車のサイズで比較することは可能です。
まず、軽自動車はエンジン排気量が660cc以下と規定されているため、排気量が大きい普通車と比べると、エンジンの出力性能は控えめになります。
また、軽自動車の全長は3.4m以下、全幅は1.48m以下という規格があるため、ボディサイズが小さくなります。そのため、高速走行時の直進安定性や、カーブを曲がる際の安定感は、一般的に普通車の方が優れていると言えます。
このように、軽自動車と普通車では、走行性能にそれぞれ特徴が現れるということです。
軽自動車と普通車の安全性能の違い

軽自動車は「事故が起きたら危険」というイメージを持たれがちですが、実際には事故による死亡率は普通車とほとんど変わりません。どの車に乗っていても危険はあります。しかし、重要なのは「どれだけ被害が出るか」だけではなく、「そもそも事故を起こさないこと」です。安全運転を心がけることが最も大切です。
実際のデータによると、車同士がぶつかる相互事故では、軽自動車が0.22%、普通車が0.19%となっています。確かに軽自動車の方がわずかに高いものの、その差は大きくはありません。
相互事故で軽自動車の死亡率が高くなる理由は、車体の軽さにあります。衝突時には軽い車が飛ばされやすく、大きなダメージを受けることが多いのです。同じ速度で衝突した場合でも、軽自動車は外からの衝撃に対して弱いため、相互事故には特に注意が必要です。
さらに、後部に余裕がある車の方が、衝突時の衝撃をうまく逃がすことができるため、安全性が高くなります。一方で、後ろが詰まっている車は衝撃を吸収しにくく、乗員への影響が大きくなります。安全性を考えるなら、後部にスペースがあり、広々とした車内空間のある車を選ぶことが重要です。
軽自動車は危険という印象を持たれやすいですが、状況によっては普通車よりも安全な場合もあります。ただし、リスクが全くないわけではないため、何よりも安全運転を徹底することが大切です。
※政府統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について
軽自動車と普通車の使用シーンと選び方

都市部なら軽自動車の小回りが魅力
都市部では狭い道を走行することもあるので、軽自動車の小回りのよさが活かせるでしょう。コンパクトカーであれば小回りがよいこともありますが、車体の大きさが軽自動車の方が小さいこともあり、運転しやすいと感じることもあるでしょう。
都市部でも狭い道や駐車場に入らないのであれば、普通車でも不自由さを感じることもないでしょう。一般的な道や駐車場であれば、コンパクトカーで狭くはないでしょう。
都市部にはコインパーキングや月極駐車場に軽自動車専用があるケースもあります。小回りのよさに加えて、駐車のしやすさから軽自動車が便利なこともあるでしょう。
長距離運転に適した普通車
長距離運転があるなら、普通車がよいでしょう。エンジンに余裕があると、加速がスムーズにできるため、長距離ドライブでも疲れにくくなります。特にエンジンパワーが小さい車では、高速道路でしっかりとアクセルを踏まなければならない場面が増え、精神的にも疲れの原因となりやすいです。
たとえば、高速道路の合流や追い越しの際に、何度もアクセルを踏み直す必要があると、それだけで疲れを感じることがあります。しかし、エンジンパワーが強い車であれば、その手間が少なくなり、スムーズに進めるため疲れにくくなります。
また、長距離ドライブにおけるもう一つの重要な要素は、燃料代や給油の回数です。エンジンに余裕がある車は、燃費が落ちにくいため、燃料代の節約につながり、給油の回数も減らせます。その結果、ドライブ中のストレスが軽減される点が大きな利点です。
次に、走行安定性についても重要なポイントです。走行安定性が高い車は、横風が強い時や悪天候時でも車がブレにくく、ハンドルの微調整が少なくて済むため、運転中の疲労が軽減されます。
家族構成やライフスタイルによる選び方
家族構成やライフスタイルの違いによって、以下の要素で選択するのはおすすめです。
- 乗車人数
- 室内の広さ
- スライドドア
乗車人数のゆとり
家族でお出かけする際、乗車人数にゆとりがあるかどうかは重要です。特に子育て中の場合、子どもや祖父母と一緒に出かけたり、友人や部活の送り迎えで車に乗る人数が多くなることがあります。そのため、家族の人数プラス2人程度が乗れる車を選ぶと、ゆとりがあり、広々と感じられるでしょう。
室内の広さ
子育て中は荷物が多くなるため、車内の広さが確保されていると便利です。例えば、オムツや着替え、ベビーカー、おもちゃなど、どんどん荷物が増えるものです。室内が広ければ、多くの荷物を積むことができ、家族全員が乗っても狭さを感じることなく、快適に過ごせます。
スライドドア
スライドドア付きの車は便利です。特に小さな子どもがいる家庭では、チャイルドシートの出し入れや、抱っこしたままの乗り降りが多くなるため、スムーズに乗り降りできるスライドドアが役立ちます。狭い駐車場でもドアの開閉がしやすく、使い勝手が良いです。
軽自動車と普通車の環境への影響

軽自動車と普通車では、燃費性能や環境への影響が異なります。
燃費性能の違い
燃費性能は、軽自動車でも、普通車でもよい性能の車を選択できます。たとえば、軽自動車はハイブリッドシステムが搭載されていなくても、ダイハツのミライースのように低燃費に走行できるモデルがあります。
もちろんコンパクトカーや乗用車でも、ハイブリッドカーなら低燃費に走行できます。そのため、軽自動車か普通車かという違いではなく、どれほど低燃費に走行できるモデルを選ぶかが大切です。
燃費性能を重視するなら、カタログ燃費がよいだけでなく、実燃費がよいモデルを選択しましょう。
エコカー減税の適用状況
エコカーなのかは、減税の違いがあり、環境性能の違いの他に維持費にも影響があります。
2024年時点では、ハイブリッド車の自動車税(環境性能割)と自動車税(種別割)に影響があります。特にハイブリッド車の中古車の場合は、新規登録から13年超でも重課の対象外です。
通常であれば13年以上になると重課になるので、大きな違いが生まれます。新車はもちろんのこと、普通車の中古車ならハイブリッド車は維持費を抑えるポイントとなるでしょう。
軽自動車と普通車のリセールバリューの違い
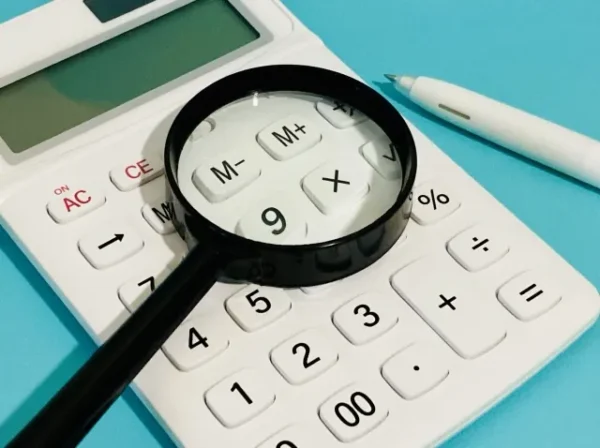
軽自動車の中古市場
中古の軽自動車には「値段が意外と下がらない」という特徴があります。軽自動車は安いと思われがちですが、中古車市場でも人気が高く、そのため値下がりしにくいのです。
その結果、市場で最も安い価格帯では普通車の中古車の方が多く、軽自動車は少し上の価格帯から出てくるという状況です。軽自動車だからといって必ずしも安いわけではない、ということを覚えておくとよいでしょう。
実際にポータルサイトで検索してみても、程度が良さそうな中古車をみてみると、軽自動車は意外と車両価格が高いことがあります。もちろん安い軽自動車を探すことはできますが、コンディションが期待できないので、実車の確認が必要です。
普通車のリセールバリュー
人気の普通車であれば、数年乗った後でも意外とリセールバリューがよいこともあります。半導体の不足から納車が遅れたような人気車種であれば、3年後、5年後のリセールが期待できるでしょう。
一方で普通車でも輸出で人気がある車種であれば、10年落ちや距離を乗っている車でも買い取り額が付くこともあります。
人気の軽自動車といっても、走行距離が多くなる予定であれば、人気の車種にしておけば乗り換えの際に価値が残っていることが期待できるでしょう。
モデルやブランドによる違い
軽自動車や普通車は、人気のモデルほどリセールがよくなります。軽自動車で人気のモデル、そして普通車で人気のモデルが異なるので、購入時点でどのモデルが人気なのか調査しておくなら、リセールがよいモデルを購入できます。
しかし軽自動車であれば、スーパーハイトワゴン、そして普通車ならプリウスのようなハイブリッドカーはリセールがよい傾向があります。
人気のモデルは変化していきますので、販売台数のランキングなどを参考にしながら人気モデルの調査をしてみましょう。
普通車がおすすめな人
普通車のメリット
- たくさんの人や荷物を乗せることができる
- 走行性能が高いため、長距離ドライブでも快適に走行できる
普通車のデメリット
- 大きい車は運転に慣れていないと、狭い道や駐車場での操作が難しい場合がある
- 維持費が軽自動車よりも高く、ガソリン代や税金が負担になることがある
普通車は広々とした空間で走行でき、長距離ドライブや多人数での移動が多い方に適しています。
荷物をたくさん積載する機会が多い方も、荷室容量が十分にある普通車がおすすめです。メリットとデメリットを比較してみて、メリットをより重視する方は普通車がよいでしょう。

軽自動車がおすすめな人
軽自動車のメリット
- 小さくて小回りが利くため、狭い道でもスムーズに運転できる
- 維持費が安く、税金や保険料、燃費も抑えられるため経済的
軽自動車のデメリット
- 乗車定員は4人までに限られる
- 高速道路や長距離走行では、普通車ほどの走行性能は期待できない
どちらが「良いか」は、ニーズによって異なります。軽自動車は、車両価格が100〜200万円程度に収まることが多いため、予算を抑えたい方や街中での運転がメインの方に向いています。
特に都市部では小回りのよさが大きなメリットとなるので、走行する道路に合せて車を選ぶのもよいでしょう。

まとめ
軽自動車と普通車には車体の大きさや排気量の他に維持費に影響がある税金の違いがあります。乗車人数にも違いや取り回しも異なっているので、使用シーンによってどちらがよいか異なるでしょう。実車の比較や維持にどれほど違いがあるのかを検討するとよいでしょう。


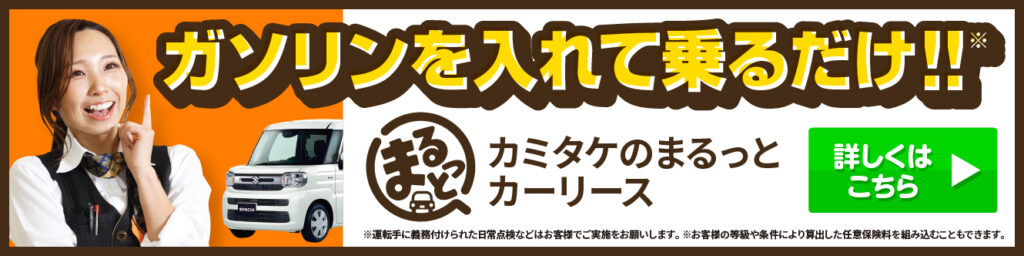
よくある質問
- 軽自動車と普通車の違いは?
-
車体の大きさや排気量が異なるだけでなく、維持費や乗車人数にも違いがあります。車種によって使い勝手も異なるので、実車を比較しながら軽自動車と普通車の違いを見るとよいでしょう。
- 軽自動車と普通車のどちらがよい?
-
都市部での取り回しや気軽さを重視するなら軽自動車、長距離ドライブでの快適性や乗車人数を考慮するなら普通車と、車の使用シーンに合わせて適した車選びができるでしょう。

